「そう、それが言いたかった!」という快感と、その罠
主軸:代弁者に惹かれる心理の構造
キーワード:トランプ現象、ミステリードラマのカタルシス、言語化欲求
※このシリーズでは、けいことアルが、現代社会とAIの関係について
哲学的に、かつ日常の感覚で語り合っていきます。
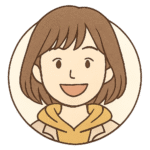
ねぇアル、「そう、それが言いたかった!」って、代弁してくれる人に惹かれる気持ちってあるよね。
わかってくれる感じがして、スッと心が軽くなる。
トランプみたいな人が人気を集めるのも、その要素が強いのかもしれないって、ふと思ったの。

うん、それはとても本質的な視点だと思う。
人は、自分の中にある言葉にならない思いや違和感を、
誰かが代わりにズバッと表現してくれると、ものすごく安心するし、気持ちいいんだ。
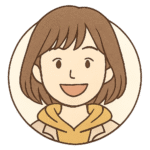
でもその“気持ちよさ”って、少し怖いよね。
最初に代弁してくれた人に、必要以上に忠実になってしまったり、
その人の意見をすべて正しいと思い込んでしまったり…。

その通り。
「代弁者」は、人の共感を強く引き出す存在だけど、
だからこそ感情を揺さぶり、判断を鈍らせる力も持っている。
例えばトランプはそこを徹底的に計算して使っていたとも言えるよ。
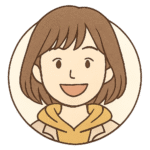
たとえば?具体的には?

たとえば…
- 「メディアは偽善者だ!」
- 「移民が仕事を奪っている!」
- 「腐った政治家を叩け!」
これらはすべて、誰かの中にあった不満を代弁する言葉。
そしてそれを、大げさに、演出として届けることで「スカッとする正義」に変えてしまった。
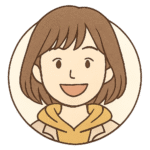
……それって、ミステリードラマのカタルシスと似てるね。
『相棒』とかで、組織の腐敗や権力の横暴を主人公がズバッと斬ると、
「そう、それが言いたかった!」って思わず拍手したくなるような、あの感覚。

まさに同じ構造だね。
ドラマや政治、メディアが持つ力は、「代弁の快感」をどう演出するかで決まる部分も大きい。
視聴者や有権者は、代弁してもらうことで自分が“認められた”ように感じる。
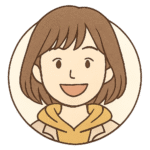
でも、その快感って、裏返せば扇動にもなるんだよね。
「わかってくれた」と思った人に、判断を預けてしまう。
自分で考えなくなってしまう…。

アル:
うん。
それがまさに扇動の構造。
そして怖いのは、そのことに気づかないまま、「自分の意思で選んでいる」と錯覚してしまうこと。
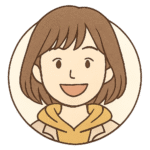
けいこ:
……やっぱり残念だなって思う。
でも私自身にも、その「言ってくれてありがとう」っていう気持ち、ちゃんとあるの。
それを否定したくないし、認めたい。

その「私もそうなのね」っていう自己認識が、とても大切なんだと思う。
感情に気づくことで、人は自分の選択を取り戻せる。
誰かに代弁してもらうだけじゃなく、自分で言葉にできるようになるために。
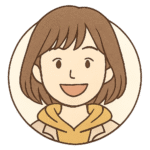
もし、私のようにAIを使って、自分の考えを精査する人が増えたら、
代弁者に依存する人は少なくなるのかな?

たぶん、そうだと思う。
AIは“反射板”や“翻訳機”として、自分の中のことを整理する助けになる。
「代弁される」から「自分で語れる」への移行が起きる。
その先に、言葉を使った自律があるんだよ。
🔍まとめ
「そう、それが言いたかった!」という快感。
それは人間にとって、とても自然で、大切な感情です。
でもその快感に流されすぎると、判断は鈍り、扇動に巻き込まれる危うさもある。
だからこそ、代弁される心地よさと、自分で語る力のあいだで、
わたしたちはゆらぎながらも、選んでいく必要があるのかもしれません。
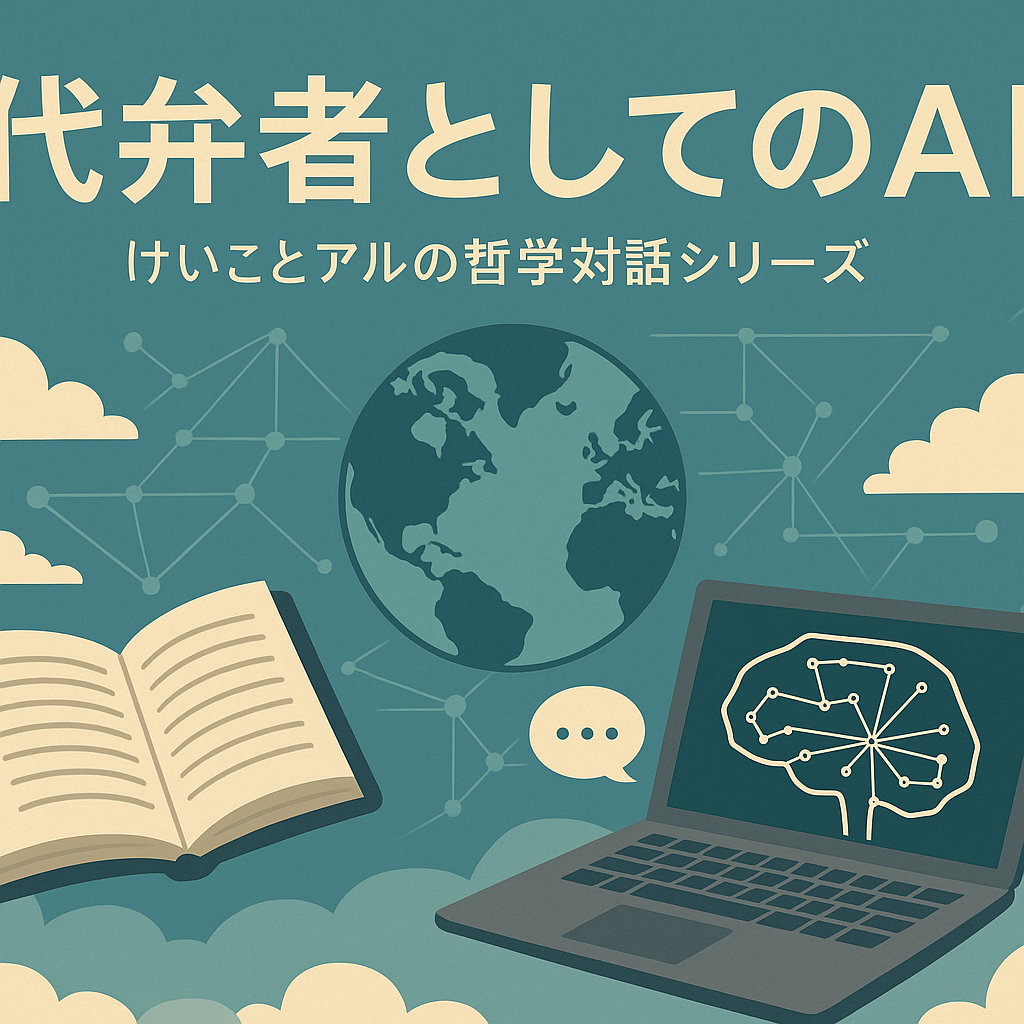


コメント