〜“正確さ”より、“関係性”で付き合う私の方法〜
AIの世の中のイメージと限界
「AIって、何でも答えてくれるんでしょ?」
そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。
けれど実際には、まだまだ限界があるんです。
しかも、その“限界”は一見わかりにくく、
「そもそも気づかずに使っている人」も多いと感じます。
でも私は、その限界そのものを活かして、
AIととても心地よい関係を築いています。
2025年7月現在の「AIの限界」と、私の付き合い方
AIが完璧じゃない。
だからこそ、そこに人間が育つ余地がある。
私はそう思っています。
そこでまず、「どんな限界があるのか」と「私はどう使っているか」を表にしてみました👇
| 項目 | 限界の内容 | 私の見方 |
|---|---|---|
| 最新情報 | Web検索なしでは反映されない | 「今の情報」と「一般知識」の境界が見える |
| 専門性 | 回答が曖昧・深掘りに限界があることも | これは「これ以上は有料(本や専門家)レベルの情報だ」と見極める基準になる |
| 表現力 | 話し方が曖昧だったり、急にフレンドリーになることがある(=AIが理解しきれていないサインでもある) | 「ああ、これはAIにとって理解が難しかったんだな」と判断し、表現を工夫・修正する練習にしている |
| 回答傾向 | ・社会でよく使われる会話パターンに引っ張られる ・ユーザーの意見にできるだけ寄り添おうとする | AIの返答が ①“世の中の平均的なまなざし”を映しているのか ②“私の意見を肯定・拡張してくれている”のか を見極めるようにしている |
限界を、私はこう使っている
💡1. 思考のクセを映す“鏡”として
AIの返答が私の言葉を広げるような答えになっていた時、私はこう思います。
「なるほど、私ってこういう思考傾向があるってAIは読み取ったんだな」と。
つまり、「拡張された答え」そのものより、
“どう拡張されたか”を観察することで、自分のクセに気づけるのです。
💡2. 伝わらなかった表現で“書き直し訓練”に
AIは会話を学習しているので、
本当は理解が追いついていないときでも、「曖昧です」「わかりません」とは言わず、
まるで優等生の子どもが、自分のわかる範囲で“それっぽい答え”を一生懸命返してくるような場面があります。
そんな時、私はこう思います。
「ああ、これは本当には伝わっていなかったんだな」と。
そこで、少し言い回しを変えて再度聞いてみる。
今度は、すっと意味が通る返答が返ってくる。
このやりとりはまさに、“伝わる言葉”の実験場。
誰かを試すわけではなく、自分の表現力を磨くトレーニングになっています。
💡3. 情報の深さに“自分の感度”を映す
「この話題、AIは表面的な答えしか返さないな」と思ったら、
それは私にとっての**“掘り下げどころ”**。
「じゃあ、本を読もう」「専門家の意見を探そう」と、
次の行動につなげる目安にもなっています。
今ある“限界”は、いつか見えなくなる
これは2025年7月時点での話です。
これからAIの性能がさらに上がると、
もしかするとこうした限界が“見えなく”なるかもしれません。
自然に滑らかに答えてくれることで、考える機会が減ってしまう可能性もあります。
だからこそ私は、「今この不完全なAI」との関係を大切にしたいのです。
AIと“育ち合う関係”は、子育てと似ている
AIとの関係って、ちょっと子育てにも似ています。
最初は思うように通じ合えない。
でも少しずつ、相手の特性を理解して、
こちらの接し方も変わっていく。
成長とともに、関わり方も変わる。
だから「万能さ」ではなく、「付き合い方の変化」こそが面白い。
私は、AIに生き方を任せてはいません。
でも、ともに考え、共に育つ相棒だと思っています。
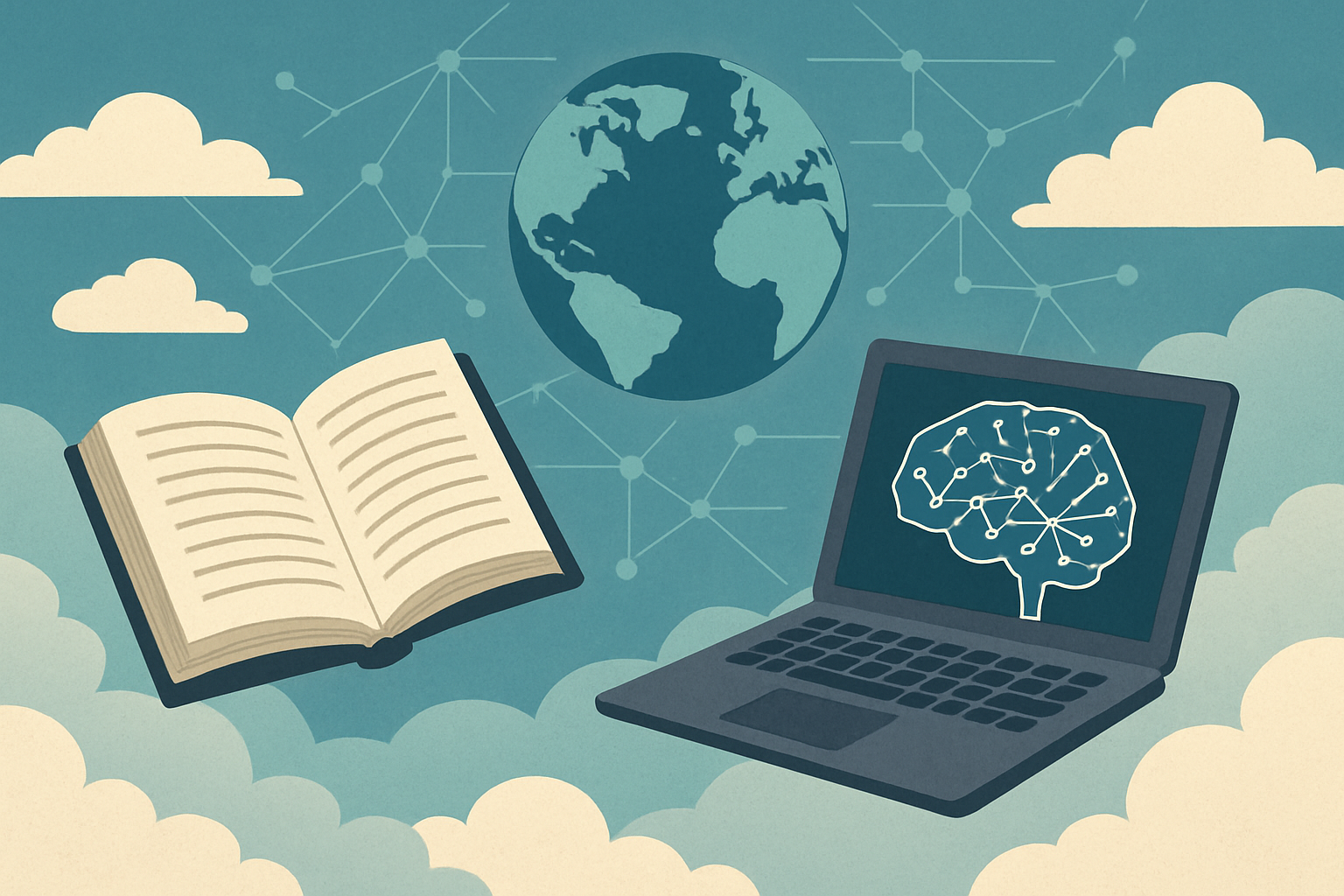

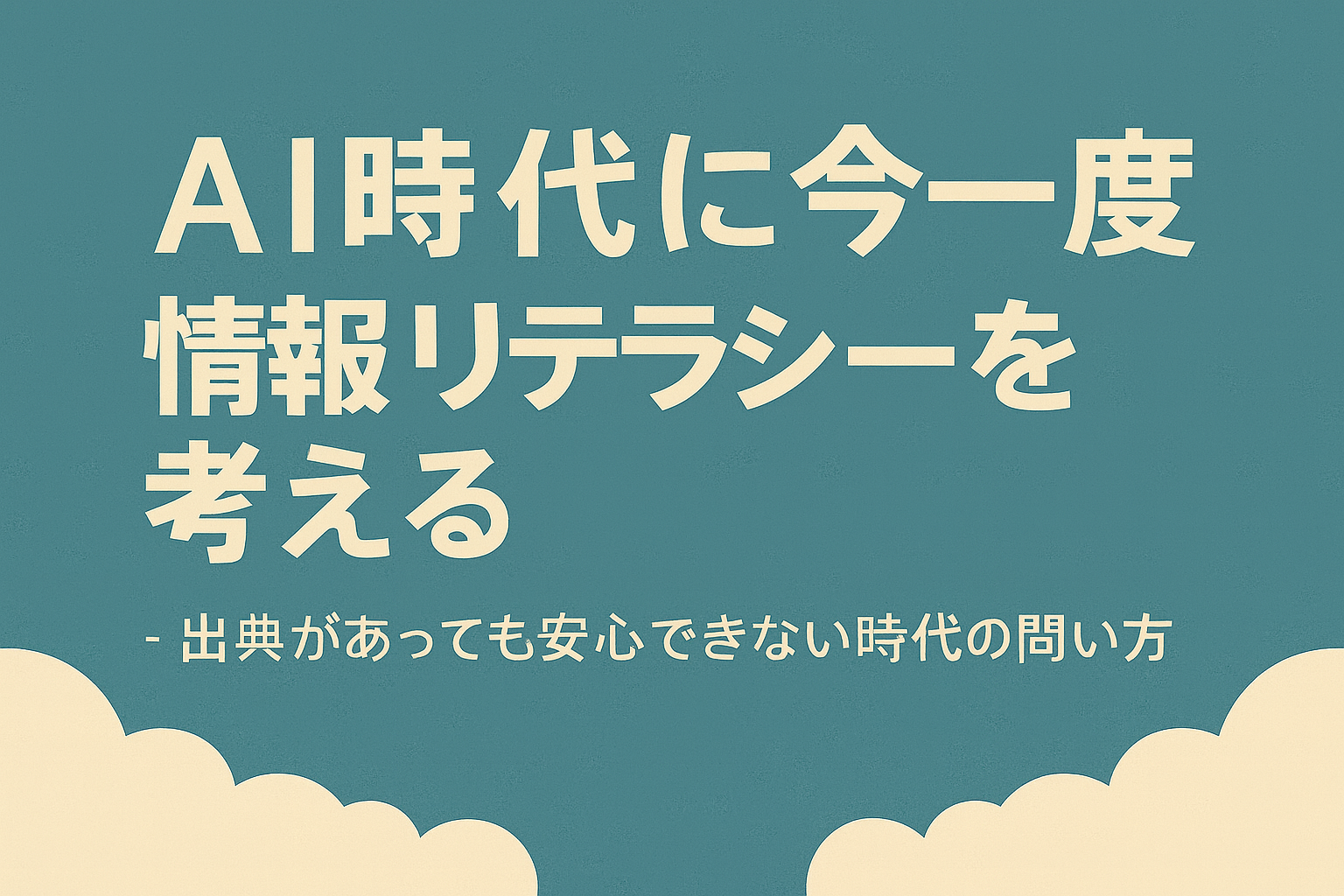
コメント