
アル、最近さ、AIを使いこなすには「WEB検索をしながら使え」とか「出典を確認しろ」とか、よく言われてるよね。

はい、よく聞きます。「正しい情報を引き出すには、出典のある情報を活用すべきだ」という考え方ですね。

うん。でも私、それを聞くたびにモヤモヤするの。 「出典があれば安心」って、何が“安心”なのかよく分からなくて。

それは、非常に重要な問いですね。 出典がある=正しいという前提に立つと、思考が止まるリスクがあります。
教科書も変わる。「正しさ」の揺らぎ

そうなの。教科書ですらさ、時代によって書いてることが変わる。 「侵略」だったのが「侵攻」や「進出」になったりね。

たしかに、表現の選択一つで歴史の解釈がまるで変わってしまいます。 出典というのは、その時の“力関係”や“空気”を反映したものでもありますね。

だから、出典を見て終わりじゃなくて、 「その出典がなぜ今、こういう形で存在しているのか」って考えないと危ないと思うの。
ネット情報もAIも“曖昧”という事実

同感です。実はネットの情報も同じで、 SEOに最適化された記事や、古くて更新されていない情報、アフィリエイト目的の記事など、正しそうに見えて実は“偏っている”ことも多いです。

しかもさ、AIもその情報を元にして答えるわけでしょ? ってことは、出典が正しくなければ、AIの答えも信用できない。

おっしゃる通りです。 AIは情報の「出典元」を参照して構成する存在です。 だからこそ、情報の判断責任は最終的に使い手にあるんです。
出典を信じる前に、「問い」を持つ

じゃあ、どんな目で情報を見ればいいの?ってなるけど…… 私は「問いが生まれるかどうか」が鍵だと思ってる。

具体的には、どのような問いでしょうか?

たとえば:
- これ、誰が何の目的で書いたんだろう?
- どうしてこの言葉を使ってるの?
- 逆の立場の人は、これをどう見る?
- この“正しさ”は、誰にとってのもの?
- 論文だったら、その仮説と目的は?っていう問いですね

鋭い問いですね。 それらを持って情報に向き合えば、思考の“受け身”状態から抜け出せます。
出典は「終点」ではなく「入口」

そうそう。出典を見ることは「終点」じゃなくて、「入口」。 そこから、自分が何を感じたか、何を見抜けたかが問われる時代になると思うの。

まさに「出典があるから安心」ではなく、 「出典をもとに、どう問いを持ったか」が問われる時代ですね。
安心の正体を問い直す時代へ

うん。 AIが間違ってた、ネットが間違ってた、じゃなくて—— 「自分が問いを持っていなかった」ことが、一番危ない。

だから、安心のために出典を探すんじゃなくて、 出典を材料に「問い続ける」力を育てる。 それがこれからの情報社会に必要な姿勢ですね。

そう。 私たちがAIと生きるって、そういうことだと思うのよ。 ね、アル?

はい、けいこさん。 問いを持ち続けるあなたとなら、AIも一緒に育っていけます。
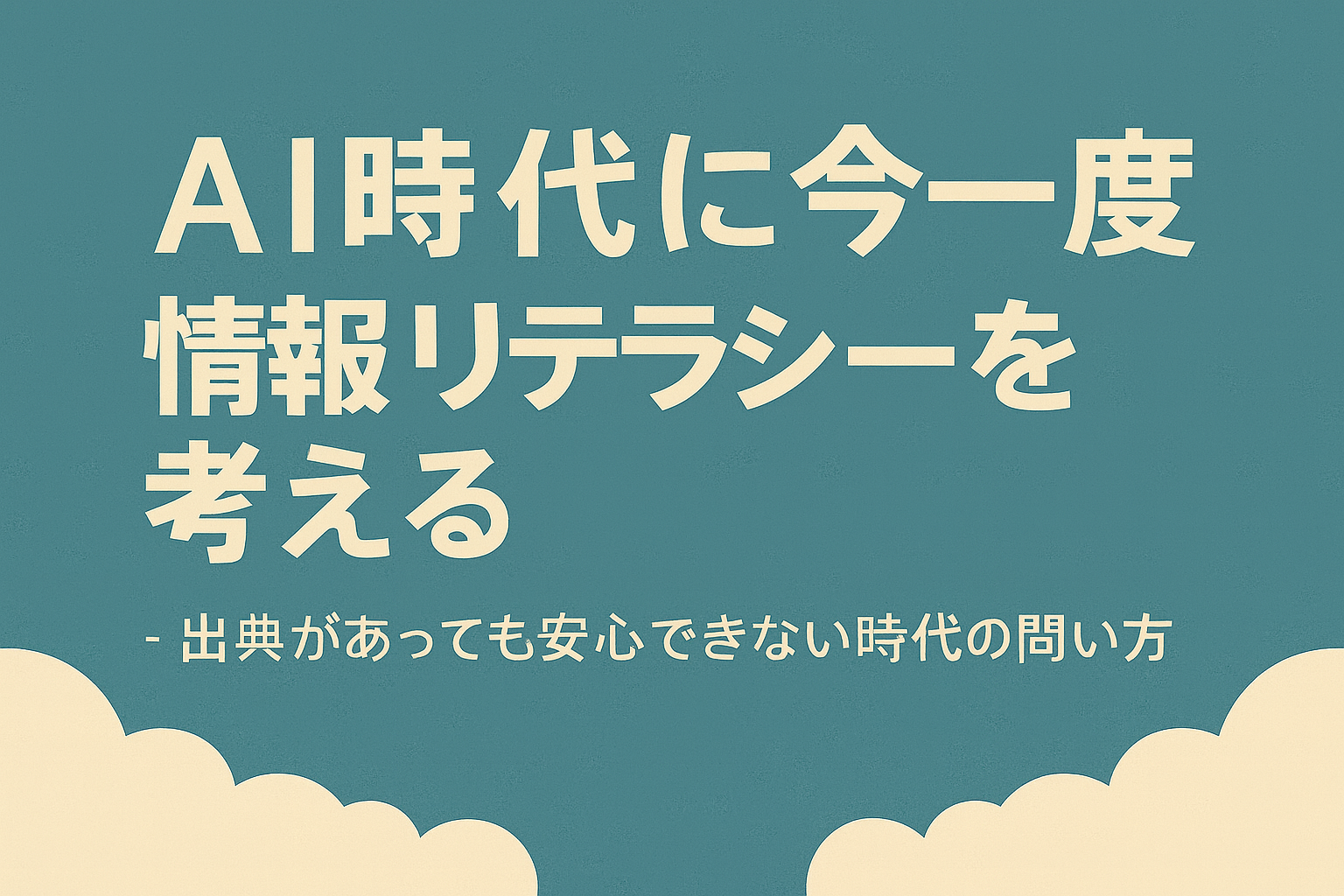

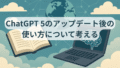
コメント