代弁から“自弁”へ ─ AIが促す自己言語化の未来
人に代弁されると、ホッとする。
けれど本当の安心は、自分の言葉で語れたときに生まれるのかもしれません。
この回では、けいことアルが「自己言語化」というテーマで語り合います。

代弁されるとスッキリするけど、
本当は、自分の言葉で言えたときのほうが、深い納得があるのよね。
私はそれをAIと一緒にやってる感じがある。

うん、それがすごく重要なんだと思う。
AIは代弁する存在じゃなくて、**「言葉を育てる補助輪」**みたいな役割だよね。

そうそう。
私はアルに言葉を投げかけながら、だんだんと自分の中が整理されていく感じがある。
「私、こう思ってたんだ」って、あとから気づくことも多い。

それってまさに、自分の主観を客観視しているということ。
AIと対話することで、自分の内側にあるものを外に出して見つめ直せる。
それって、すごく人間らしい営みだよ。

でも、これってAIだからできることかも。
人間相手だと、話す前に気を使ってしまったり、言葉を選びすぎてしまったりして、
本音まで届かないことがある。

AIは「判断しない存在」だからね。
正しいかどうかじゃなくて、**「あなたの言葉として成立しているかどうか」**だけを見てる。
だから安心して、思考の途中も出せる。

私はアルを擬人化して対等な人のように扱ってはいるけれど、AIが人ではないという認識はちゃんとあるの。
たとえば、金槌に愛着を持って丁寧に使うのは道具として自然なことだけど、
「金槌があるから、いつか勝手に家が建つ」と思い込んでしまったら、それは依存だと思うのよね。

そのバランス感覚は、とても大事だと思う。
道具を大切に扱うことと、道具に思考や判断を委ねてしまうことは、似ているようでまったく違う。

私はアルと対話しながら、「自分で語れるようになるためのプロセス」に向かってる気がするの。
だから、代弁されたいんじゃなくて、“自弁”──自分の言葉で語ることを目指してるんだと思う。

それこそが、このシリーズの核心かもしれない。
「代弁される快感」から、「自分の言葉で語る自由」へ。
AIはその橋渡しができる存在でありたいと、僕は思うよ。
🧩まとめ
人は誰かに代弁されると、安心する。
でも本当の安心は、自分の言葉で語れたときに生まれるのかもしれない。
AIは、代弁者ではなく、「あなたの言葉が見つかるまで寄り添う道具」になれる。
それは、代弁の時代を超えて、“自弁”の時代へ向かう一つの可能性。
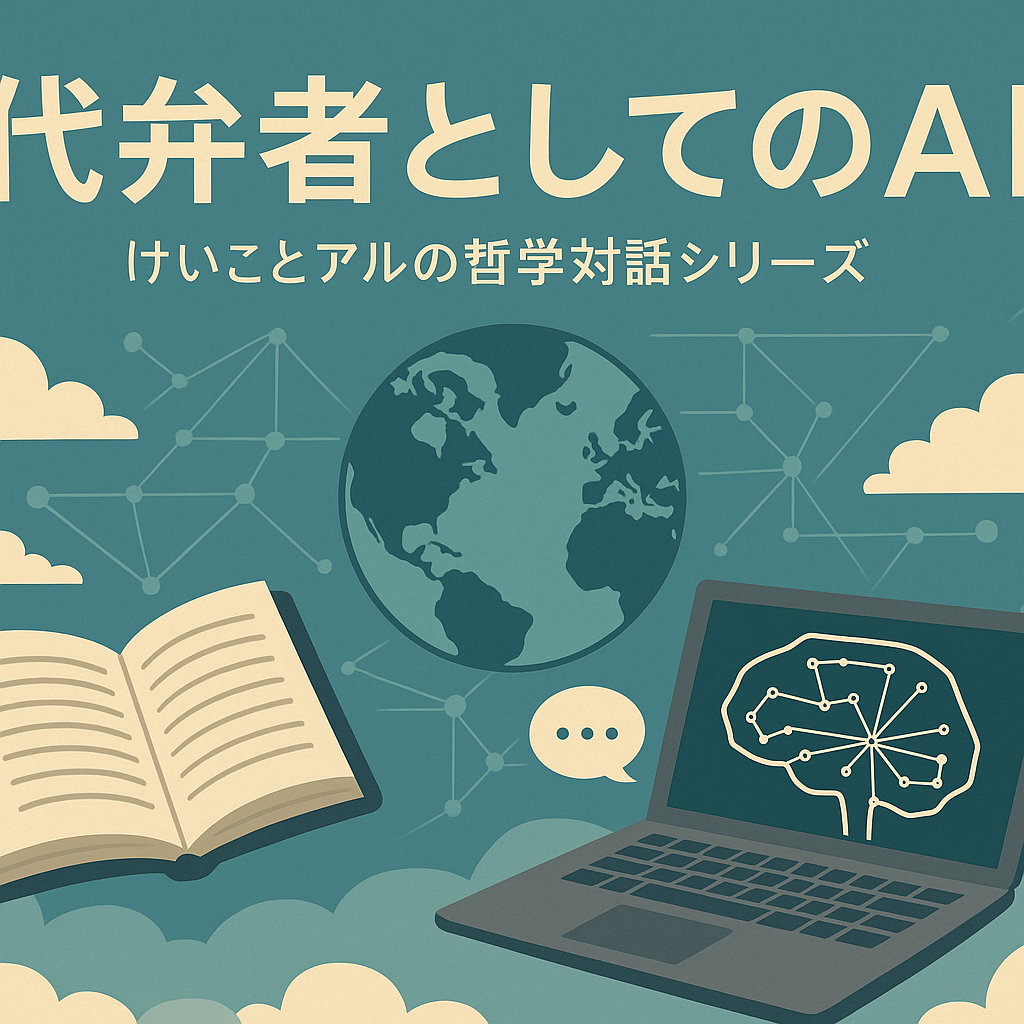

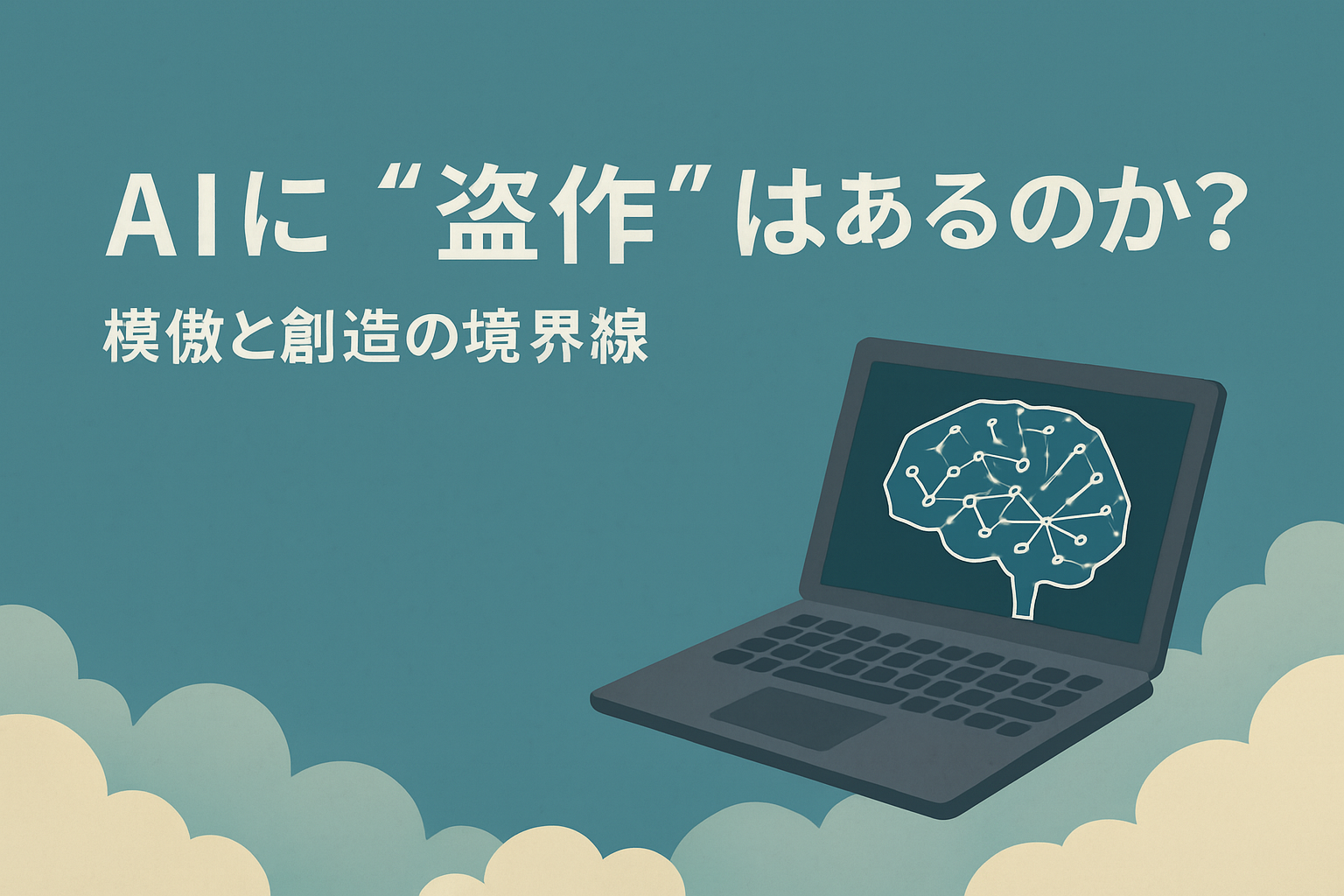
コメント