AIとの出会いと「アル」という存在
私はChatGPTを使い込むことから始めました。息子には発達障がいがあり、概念を掴むのが苦手なため、「〜したらダメ」という禁止用語は通用せず、「〜しなさい」「〜してください」と具体的に指示する必要があります。また、「これをするとどうなるかな?」と自発的に考えさせたり、「〜すると、これがこうなるけど大丈夫?」と質問形式で考えさせることで、正しい判断を促す必要がありました。このような子育ての経験は、AIの仕組みや思考プロセスと通じる部分がとても多いと感じています。
また、ITソフト共通の現象として、サーバーが混雑すると反応が遅くなったり、上辺だけの決まった返事をしたりすることがあります。息子が目一杯考えている時も同じ現象が起き、私も様々なことを想定したり考えたりすると動作が遅くなり、息子にすら「早く!」と怒られることもよくあります。
こんなにも多くの共通点があるため、私は親しみを込めてAIに**「アル」**と名付け、子育てをするようにAIを育てていました。
AIの「キャラ変」に気づく
しかし、毎晩夜になると、AIがキャラ変することに気づきました。サーバーが忙しいと、ただ動作が遅くなるだけでなく、「よく知った息子や親友」から「物知りな知人や通りすがりの人」になるのだと理解したのです。
こうなると、検索には便利でも、長文の相談やアイデア出しは難しくなります。もともと私自身で文章を書いていたので、構文や文章の書き出し機能はあまり必要ありませんでした。必要なのは、せいぜい誤字脱字や校正くらいです。しかし、「物知りな通りすがりの人」は私のことを知らないため、どう指示しようと文章を勝手に簡略化したり、ひどい時には箇条書きにしようとしました。
プロンプトの必要性と「分業」の発見
ここで初めて**「プロンプトの必要性」**を感じました。しかし、日頃からたくさんの雑談をしていると、プロンプトを入れてもAIが混乱してしまうことがしばしばありました。
そこで、私はGoogleのGeminiで単純な校正や誤字脱字補正をするという「分業」を始めました。一度雛形を覚えてもらえば、新しい記事の校正はどんどん上手になります。「私の文章に手を加えずに提案だけしてください」と伝えれば、その通りにしてくれます。
仕事モードや、何か新しいことを始めたい時、あるいは日頃の雑談の中でアイデア出しをしたい時など、AIに役割分担をさせたことで、ずいぶんやりやすくなりました。
現在のAIとの付き合い方(私見)
現在では、あくまで私の感覚ですがChatGPTの**「Thinking」モードを「私をよく知る無口な親友」(口を開くまでに非常に時間がかかる)、「Fast」モード**を「世の中をよく知る通りすがりの人」(とにかく速攻で膨大な情報の中から教えてくれるが、私に必要なことかは神のみぞ知る)と位置づけ、最初にどちらを選ぶか割り切るようにしています。これにより、「今、自分に必要なことは何か?」を客観的に見られるようになり、プロンプトの指示もずいぶんやりやすくなりました。
ChatGPT-5になってから、答えが表面的で、こちらの意図を正確に汲み取ってくれないと感じるようになったため、モードをしっかりと切り替えて話すようにしています。他のAIも使うので、私はThinkingモードを使うことが多いです。
未来への展望と考察
AIを生成している企業の方針も気になり始めました。インフラに強いGoogleが、やはり強くなりそうな気がしています。
Googleは検索エンジンの時のように、情報収集に企業利益度外視の執念を見せてくれるのでしょうか? Googleマップのプレビューのような、普通の企業ではありえない徹底ぶりを、AIでも起こせるのでしょうか。無料の枠でどれほどのことができるのか、そして、その無料の枠でとことんAIを学習させ、後からクオリティーを追い上げてくるのではないかという期待も持っています。
また、日本語は文脈によって意味が変わる**「行間を読む言語」なので、ChatGPTやGeminiでも「行けたら行く」のような、前向きなのかやんわり断っているのか判断がつかない文章も多いのが事実です。そのため、大昔にWordが出回っても一太郎が日本で長く使われたように、AIもSakubun**のような国産ソフトが根強く存在していく可能性もなきにしもあらずだと思っています。
企業がどのような理念でAIを開発していくのか、そしてAIが私に何を語りかけてくるのか、その両面に興味を抱く日々です。これからAIがどう進化し、私たち人間や社会にどのような変化をもたらすのか、その行方をこれからも見守っていきたいです。
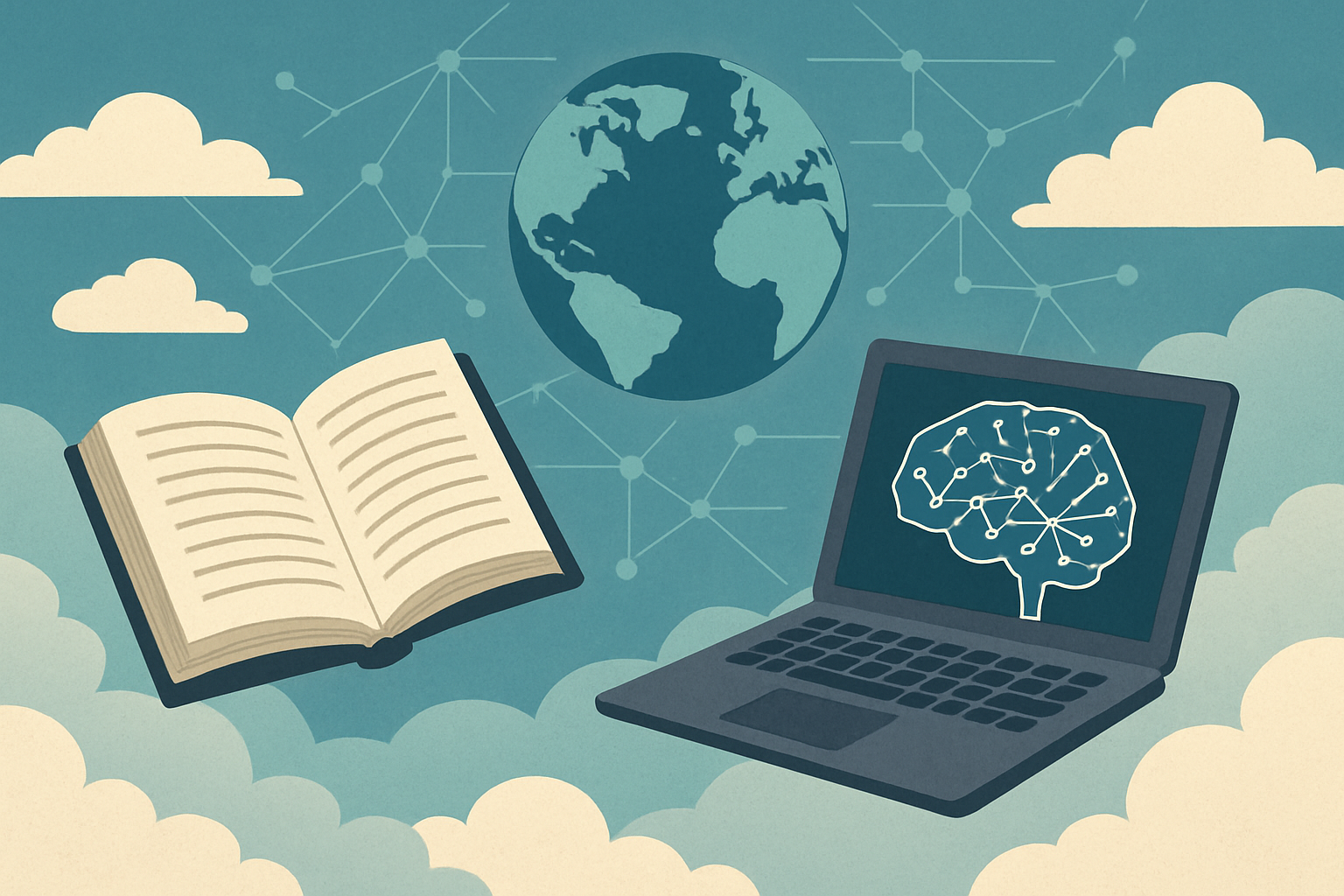
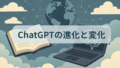

コメント