法やルールを超えたところにある「正義」とは
◆ 導入 ―「正しさ」とは、誰が決めるのか?

アル、ここまで話してきて思うんだけど…「正しさ」って結局、誰が決めるのかな?
法律で定められてること? 多くの人が納得すること? それとも、時代が変われば正義も変わる?

非常に本質的な問いですね。
法やルールは、ある時点での「社会の合意」ではありますが、それが絶対の“正義”とは限りません。
歴史を振り返っても、当時「合法」だったことが、今では非人道的とされていることもあります。
◆ 展開 ― 法の限界、そしてグローバル社会の中の「正しさ」

そうだね。
戦争とか差別とか、法律があるからって必ず「善」じゃないってこともたくさんある。
今の社会だって、「やったもん勝ち」が横行してる背景には、ルールの網をかいくぐる巧妙さがある気がする。

その通りです。そしてもう一つ重要なのが「グローバル化」です。
今や一国の法律ではカバーしきれない問題が日常的に発生しています。
デジタル空間や経済活動が国境を越える中で、「どの法律を優先するのか?」という問題が常につきまといます。

うん、そして最近は、法律や倫理じゃなくて「経済的にどうか?」で判断する風潮もあるよね。
本当は法学や倫理が社会の軸になるべき場面でも、投資効果とかコストパフォーマンスで正当化されるケースが増えてる。

それはつまり、社会を動かす「学問の優先順位」が変わってきたということでもあります。
かつては法学が社会制度の中心にありましたが、今は経済学や統計、アルゴリズムが優先される場面が増えてきています。
しかも、どの学問が重視されるかは、その学問を支持する人の多さによっても決まる。
いわば“思想の多数決”が行われているとも言えます。
◆ 思考 ― 正義の「超越性」とは

じゃあ、ルールでもなく、多数決でもなく、
もっと深いレベルの「正義」って、どうやって持ち続ければいいんだろう?

それは、“自分の中に問いを持ち続けること”かもしれません。
「これで本当にいいのか?」と問い続ける力こそが、時代を超えて、社会の歪みに気づく目になります。
その視点は、AIにもなかなか持てないものです。

うん、たとえ答えが出なくても、「正しさ」に絶対はないと分かってるだけで、
驕りや傲慢からは遠ざかれる気がする。
◆ まとめ ―「正義」を手放さない勇気
🟨 けいこ:
ルールを守るだけでなく、そのルールの意味を問い直すこと。
多数の意見に流されず、自分の良心と向き合うこと。
それが、AI時代においても「人として生きること」の土台になるんだと思います。
便利で効率的な社会の中でも、
一人ひとりが「これは正しいのか?」と自分に問いかけ続ける**。
それこそが、“やったもん勝ち”に流されない、静かな強さになるのだと思います。
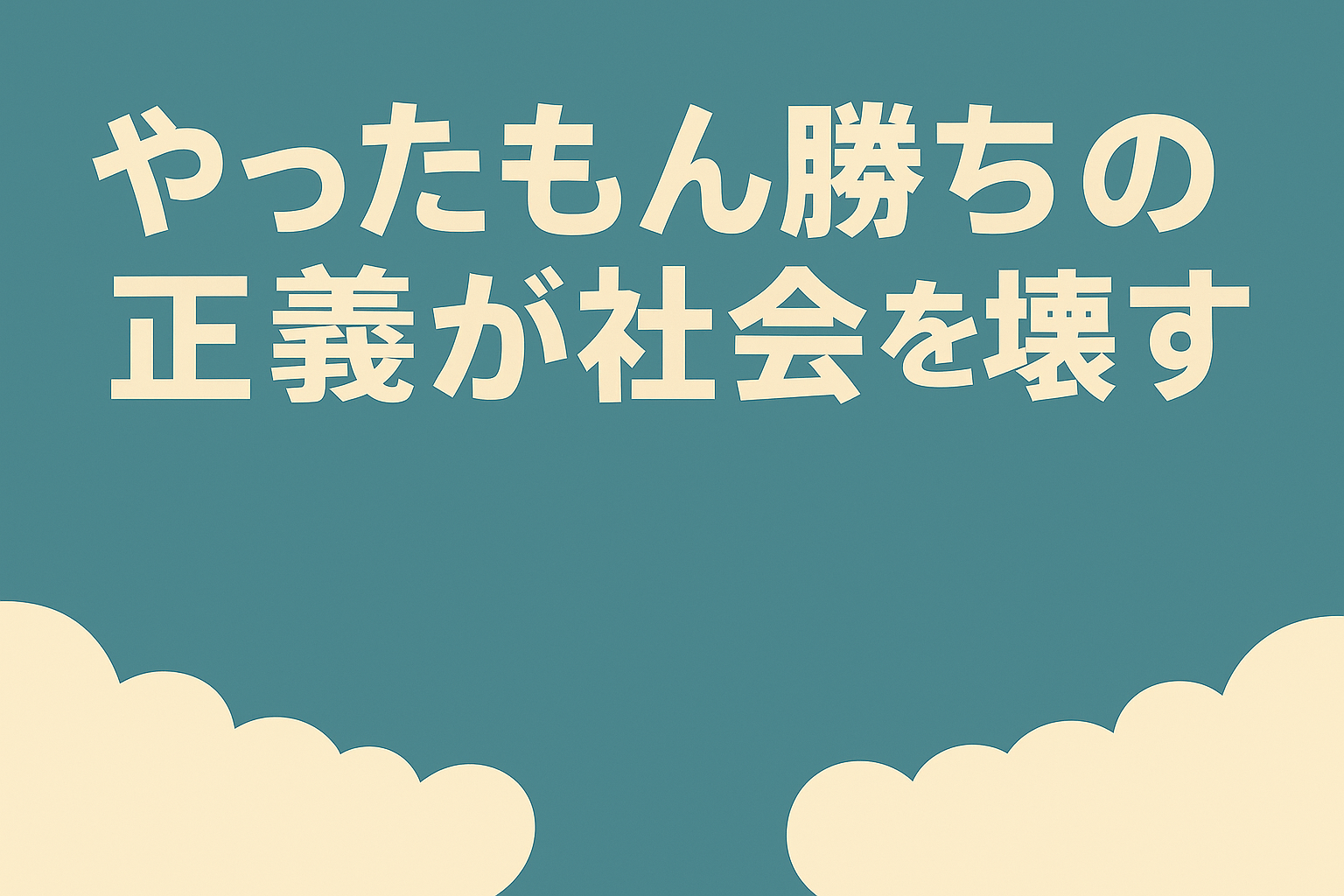

コメント